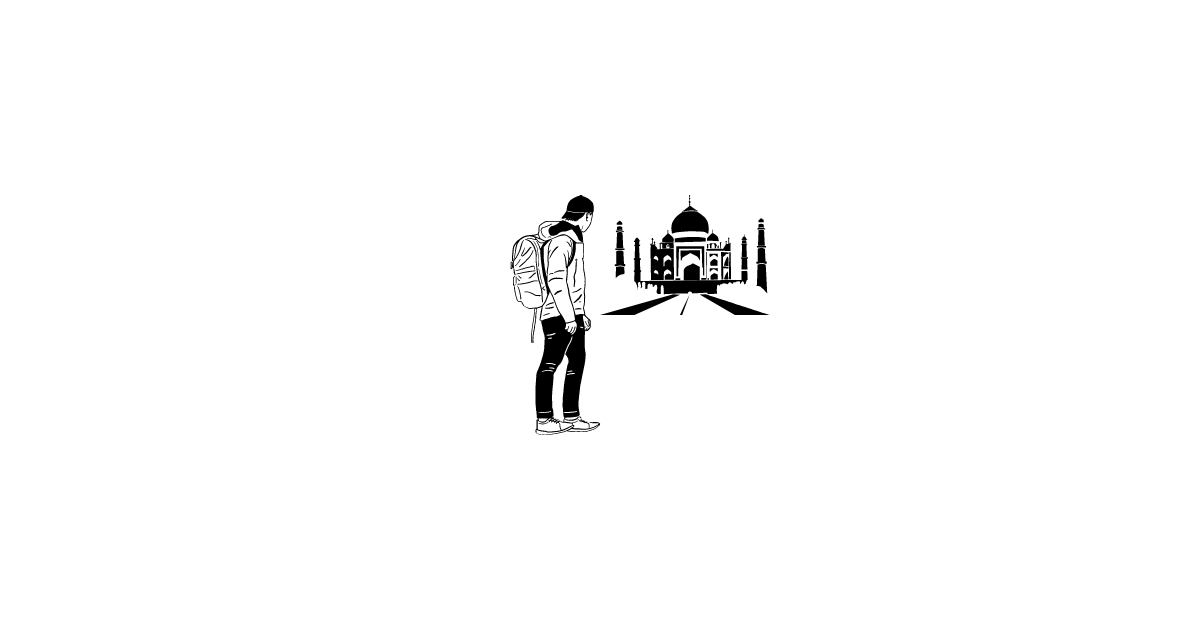
落語のなかに「雛鍔」という噺がある。
このなかに登場する植木屋の倅というのが「いかんともしがたい」こまっしゃくれた腕白で、これが笑いを誘うという根太になるのだが、最近この噺を聴いていて、ふと思い出したことがあった。
若い頃、バックパックを背負ってインドを旅したことがあるのだが、その道中で出会った、噺と同じような「いかんともしがたい人たち」のことをフラッシュバックしたのだ。
いかんともしがたい、というのは、あつかいに難儀する、まあ、困った人たちのことだが、こういう人たちというのはやっぱり、どこへ行ってもいるものである。
ここではさしづめ、まさかインドで出会うとは、といったところになるのだろうが、そんな人たちのことを記しておこうかと思う。
一人目。
その旅行ではムンバイ(ボンベイ)からチェンナイ(マドラス)まで南インドの海岸線をメインに移動し、途中、内陸の各都市にも立ち寄るといった旅程を想定し、たいがいを鉄道、あるいは長距離バスでほうぼうに寄るという移動手段を考えていた。
放浪というほどではないが、気の向くままにインドのいろいろなところを見てみたいと思っていたので、鉄道はローカル線を利用することにしたのだが、そのときのことである。
テレビなどでインドの鉄道事情をご覧になったことがある方ならご存知かもしれないが、人が列車の側面にへばりつきながら走るという風景をその旅でもなんどか目にした。
そんな列車だから、要するにハイパー満員列車状態なわけで、車内も当然、鬼混みしている。とくに三等客席がすさまじいということは事前にわかっていたので、鉄道の移動では二等客席のチケットを購入することにしていた。
で、ある路線に乗車したときに、ちょっとした事件が起こった。
自分が予約した席に、先客というか、子どもが座っていたのである。
あれ?と思ったが、なんどか確認してもやっぱり自分の取った席である。
しょうがないなと思って、カタコトの英語でその子にやんわりと「そこはわたしの席ですよ」と言おうとした瞬間──。
対面座席の前に座っていたインドのご婦人が、いきなりその子のことを有無を言わさず平手打ちし、えらい剣幕で怒鳴りつけたのである。
なんぞや?とびっくりしたが、どうやら、その子の身なりが少々、すすけていたことから事情が飲み込めた。つまりは、インド社会に現実的には残存する、身分制の問題である。
そのご婦人もうすうす勘づいてはいたが、自分の登場でそれが確信に変わり、この抜け目ない子どもを叱り飛ばしたかったのだろう。子どものほうも、悪態をつきながら一目散にその場から去っていった。
衝撃の光景を目の当たりにしたものの、困ったのは、その後であった。
このご婦人、あくまでも善意を成したとの気持ち良さから、終始ご機嫌で、やたらとこちらにフレンドリーに接してくる。インドの慣習では女性のほうからあまり男性に話しかけることはないと聞いていたのに、このおばさん、年齢のせいもあるのか、やたらと話しかけてくる。
まいったなと思いながらも、相手はニコニコしているし、どうしようかと思っていたところに、車内の物売りがこちらにやってきたので、すかさず掴まえて、いちおうはお礼ということでカップのチャイをごちそうしたら、輪をかけて上機嫌になった。
こちらも作り笑顔を向けながら、内心、このおばはん、さっき子ども殴っとたしな、と思いつつも、不承不承に話に付き合うしかなかった。
結局、このインドのおばさんが途中下車していったことで、この話は終わるのだが、最後までどこか正義をなした晴れやかさ漲る様子にあてられて、げんなりしてしまった次第である。
いかんともしがたい、こういう人はどこの国にもいるのだろうなと、ため息しか出なかった。
二人目。
インドの内陸都市であるバンガロールから、インド大陸の突端にある街カーニャクマリまで移動しようと、深夜バスに乗り込んだときのことである。
大都市からの乗車だったこともあってか、偶然にも、そのバスに自分を含めて3人の日本人が乗っていた。
他の場所で日本人にあまり遭遇しなかったので、けっこう珍しいことだと思ったのだが、出発してしばらくすると、そのうちの一人の日本人旅行者がこちらに話しかけてきた。
旅をし始めて数ヶ月は過ぎていた頃合いである。日本語の話し相手に飢えていたこともあって、旅の情報交換とばかりに話も弾むこととなった。
興味深かったのが、その話しかけてきた旅行者の男性、じつは相棒と2人旅のはずだったのだが、相方のほうがインドに到着して1週間でインドという国に拒絶反応を起こしてしまい、ホテルの部屋に閉じ籠っているという。
インドについては昔から、合う人は合うが、合わない人はとことん合わない国だと言われるのだが、そのご友人は合わないほうを地でいってしまったそうだ。
とくに食事がダメだったそうで、ホテルに籠ってずっとビスケット食ってますよ、と話していた。
それで、どうされたんですか、日本に戻られたんですかと尋ねると、それでも飛行機の往復チケットを買ってしまった手前、すぐに帰ることはせずに、帰国便が出る空港近くのホテルに陣取っているという。気を遣われて、俺はダメだが、お前だけでもインドを堪能してきてくれと、そのホテルで帰りを待っているという、なんとも健気で、しかも気の毒な話だった。
ということで、相方を置いて、どういうわけか一人旅をしているという、こちらも気の毒なその人といろいろな話に花を咲かせていると、なにやら視線を感じる。
「あの人、こっちのこと気にしてますよね」
「だろうね」
「ビミョーに話しかけづらい風貌ですよね……」
「だね。おそらく、めんどくさそうな人のような気がする……」
「ですよね……」
というのも、バスに乗車していたもうひとりの日本人旅行者の男性なのだが、まず、南インドの民族衣装である腰巻きスカート(ルンギという)を着用しており、サンダル履き、しかも上半身は、なんというか、作務衣のようなものを羽織っている。
つまりは、いでたちからして、なんとなく近づきたくない、要するに痛い、そんな風体なのである。
現在でもたまに見かけるのだが、アジアの国々に旅行して、たとえばタイに行ってタイ・パンツを履いて街歩きするのは、正直、みっともないから、個人的にはやめたほうがいいと思う。たぶん、現地の人も引いているだろう。
観光地に行って、貸し民族衣装を着てちょっと写真を撮るくらいならいい。が、観光地以外の場所で、外国人が常時、その国の民族衣装を着ているというのも、かなり不気味に映るのではないかと思う。
と、まあ、いかんともしがたい、要するに、そこのところの認識にズレがありそうな人だったので、なるべくこちらからは話しかけんとこうと思っていたら、向こうも我慢できなくなったのか、やっぱり話しかけてきたわけである。
そこからはもう、そのルンギの人の独壇場である。
今から25年くらい前の話になるが、当時、インドでは、なにやら手から奇跡の粉を出すというサイババという宗教家が注目されていて、日本でも話題になっていた。この人は、そのサイババを追いかけてインドに来たという。
この一事をとってみても、二人して、うわぁ、となったが、驚いたことに、このサイババ信者、出家僧のごとく、日本からインドへと荷物を持たずに来たという。実際、風呂敷包みというか、小さなズタ袋ひとつしか持っておらず、少々ためらわれたが、なかになにが入ってるのですかと尋ねてみると、得意顔で、パスポートと少々のカネ、それと替えのパンツ一枚と言っていた。
へぇー、という感想しか出てこなかったが、なにを勘違いしたのか、自分とインドの同化っぷりにこちらが感心したのかと誤解して、とにもかくにも自分のインド人化についての蘊蓄をしゃべり倒す。
深夜バスの道中である。そろそろ寝たいんだけど思っていても止まらない。しかも、この人、しゃべり口調が念仏のようで、おそろしく眠気を誘うトーンなのに自覚がない。しゃべり続けるその人を前に、正直、いつのまにか眠ってしまった。
初対面の見知らぬ赤の他人に話しかけられて、目の前で寝るというのは、このときはじめての経験であった。
結局、朝、バスの中で目覚めて、横を見ると、もうひとりの人相手に、まだ話し続けていた。
相手をさせられていたその気の毒な人に「寝れたんですか?」と尋ねると、ところどころ意識が飛んでたから、そのぶんは寝たと思う、といっていた。
つくづく気の毒な人だと思った。
結局、バスが目的地へ着くと、そのいかんともしがたいサイババ信者はその場で去っていたのだが、この気の毒な人とは数日、旅を帯同することになり、仲良くさせてもらった次第である。
それにしても、と思う。
インド拒絶者とインド同化者のあいだに挟まれて、つくづく気の毒な人だったなと、今でも忘れられない人物であった。
三人目。
一人旅に戻って、最終目的地のチェンナイ(マドラス)までやってきたのだが、旅程を早めるつもりはまったくなかったにもかかわらず、帰国便が出るまでに10日ほどは残っていた。
まあ、最後だし、この街でゆっくりするかと思って、ホテルもおさえてしまい、怠惰に過ごすことにした。
一日ぶらりと散策し、行きつけの食堂も決め、あとはホテルで寝てるか、その食堂でダラダラ過ごすか、チャイ屋台でタバコでも吹かすかと決め込んでいたところ、どういうわけだか、およそ平和とはいいがたい、まったく逆の状況に陥ってしまう。
たしか、チェンナイに着いて3、4日たったくらいだったと思い出す。
昼前までホテルで寝て、遅い朝食を行きつけ認定した食堂でとっていたところ、同じ店のなかの向こうのほうから、なにやら日本語が聞こえてくる。よくよく聞いてみると、関西弁だった。
最初に聞いた声は、こうだった。
「ちゃうちゃう、こっち」
「そや、こっち」
インド人ウェイター相手に、関西弁一本で意思の疎通を図ろうとする二人組の日本人女性だった。
メニューを見ながら揉めている。
英語表記もしてあるのだから、多少なりとも英語を混ぜろよと思ったが、どうやら譲る気はないらしい。ウェイターのほうもタジタジである。
いかんともしがたい、と思ったが、ダルかったので、こちらは仲介する気なぞ毛頭なく、なんとなく関わりたくないなと思って、そしらぬ顔して黙々とメシを食っていたのだが、結局、見つかってしまった。
まあ、しょうがない。日本人は他にいない状況なわけだし、風向きは当然、こちらに向くだろう。
そこからは関西弁の嵐である。
数日前に大阪から来たそうで、来たばかりでいまだ多少の不安があると言っていた。
が、しゃべっているトーンからは、まったく不安の気配は感じられない。
それにしても、と思った。
そのときの自分にとっては関西弁というものがえらく新鮮に映ったのだ。
インドにいる、ということもあったが、こちらはそのときまで生涯、関東在住、親類は東北寄りで、西日本にとんと縁がなかった。ので、まさかインドで生の大阪弁に触れることになろうとは思いもよらなかった。
そんなこともあって、向こうの藁をもすがらんばかりの勢いもあり、流れで彼女たちの旅に数日付きあうことになり、チェンナイ周辺を一緒に観光する運びとなった。
まあ、とにかく賑やかだった。
ふたりとも旅行でテンションが高いというのもあったのだろうけど、大阪の人が二人揃うと、ふつうの会話でも漫才のように聞こえるのかと思ったほどである。
面白かったのが、オーロヴィルを観光したときだった。
オーロヴィルとは、おそらく西欧のヒッピー・カルチャーの聖地みたいなところで、要するにインド思想ナイズされた人びとが世界中から集まってコミュニティを形成していて、まあ、早い話が、みんなで集まって静かな農村で”瞑想する”ような場所である。
が、ここを訪れたはいいが、自分にしてみれば、まったくピースフルな思い出はなく、関西弁のことしか思い出せない。
行くときに道に迷ったのだが、そのときも「ちゃうちゃう、こっち」「そや、こっち」である。
現地に着いて、コミュニティのなかを見てまわるサイクリング・コースがあったのだが、3人で自転車を借りて乗りつけても、「ちゃうちゃう、こっち」「そや、こっち」である。
ドタバタすぎて、まったくもってマインドフルネスにはならない。
チェンナイに戻って来て、行きつけの店で食事をしていても面白かった。
数日経過して、すでに勝手知ったるところになったのか、インド人ウェイターもふつうに関西弁対応になっている。
女子二人、いまだ関西弁しか話さないのだが、インド人ウェイターもふつうにオーダーをとっているのである。うんうんと頷いている姿がおかしかった。
英語ではなく、もはや関西弁こそが世界標準語なのではないかと思い知ったほどである。
結局こちらは帰国することとなり、帰りの空港まで見送りに来てくれて、彼女たちには楽しい珍道中を締め括ってもらって感謝ひとしきりといった具合だったのだが、それにしても、どこまで関西弁で通すのか、その後が気になるところだった。
観光の最中、いくどか英語も少しは使ってみたらどうかと話してみたものの、こう言うのである。
「あかん、思いついても、先に日本語が出てまう」
「せやな」
いかんともしがたいと思ったが、同時に、見あげたことであるとの思いも湧いた。
こういう種類の”いかんともしがたさ”は、悪くない。
そんなちょっとした、清々した気持ちにさせられた。
そんなこんなのインド一人旅ではあったが、旅のなかのこうした”いかんともしがたさ”は、思い返すと旅の旨みを引き出してくれる良いスパイスであったと思う。
人生においても、それは変わらないのではあるまいか。
もっとも、困った人に出会ってもそれを鷹揚にイナせる、そんな胆力はほしいところだが、それにしても遭遇してしまった後の祭りで、それはそれで笑えるのであれば、面白かったで済ましてもいいもののような気がする。
少なくとも自分のなかでは、旅の回想にピリリと辛味を添えてくれた、思い返せば小気味よさも感じさせる、そんな気分にひたらせてくれる人たちであった。