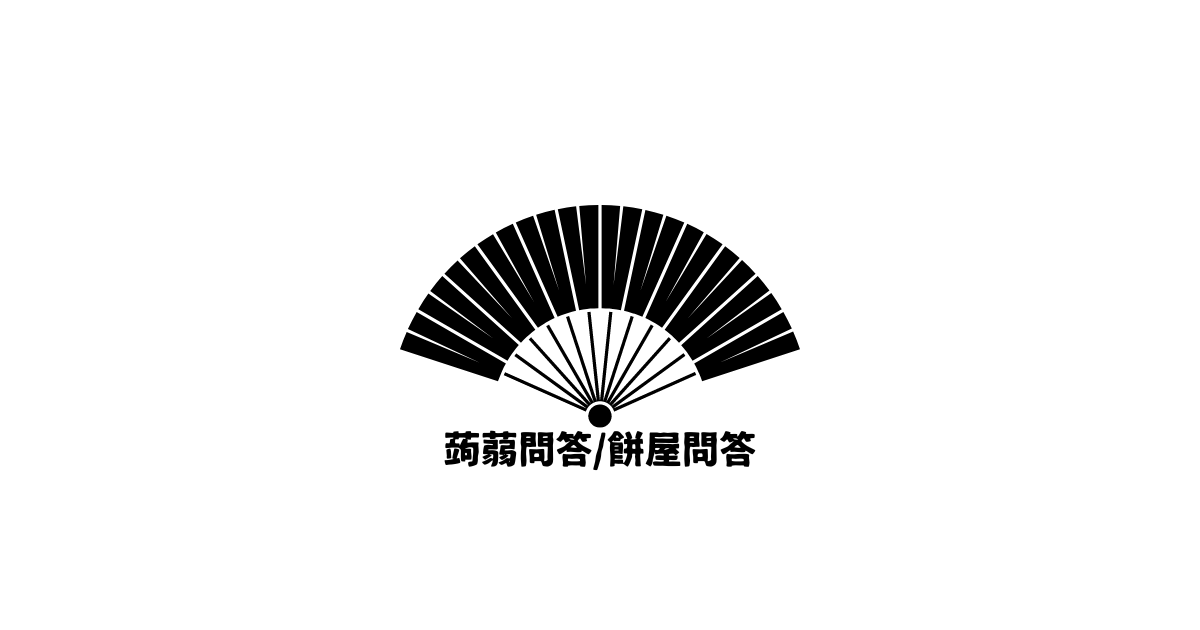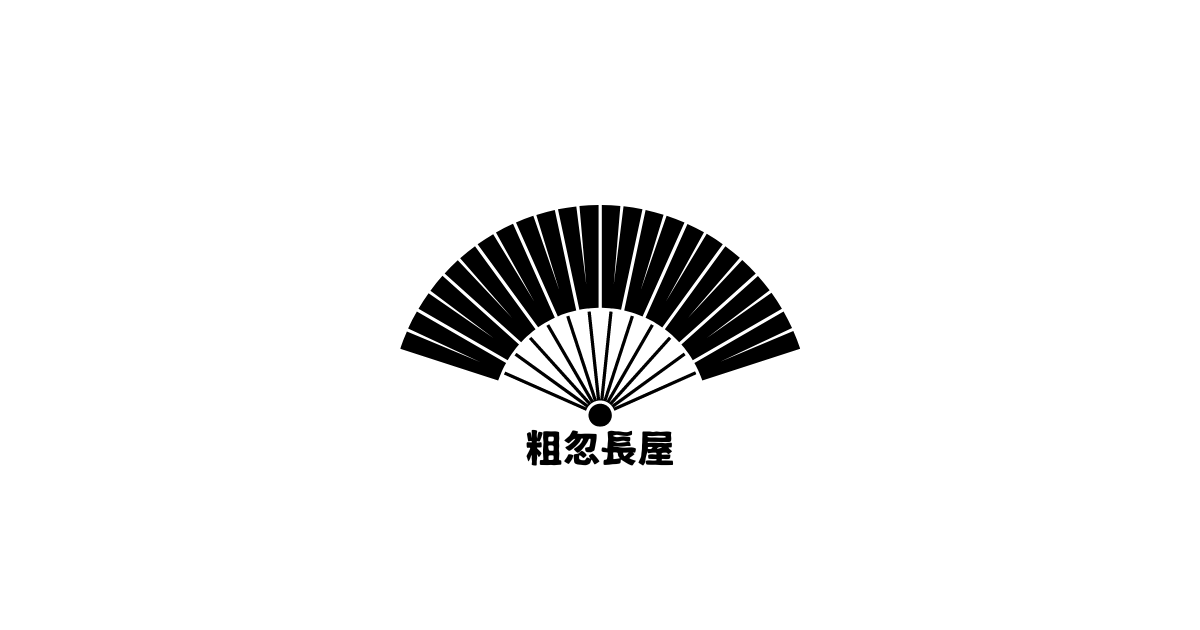男女の出逢いがマッチングアプリ全盛となった現代にあっては、あるのかどうかも疑わしい、もの珍しい"恋わずらい"を題材にした演目「崇徳院(すとくいん)」。
古風な題材ですが、雅味があり、江戸時代のほのぼのとした、微笑ましいムードを感じさせる小題です。
とても落語らしいといえば落語らしい、ドタバタ喜劇のような展開なので馴染みやすく、落語不案内の方にも、そして百人一首好きの方にも、なぜか古典全般のお勉強になるお題となっております。
◾️あらすじ
噺は、さる大家の若旦那が病で床に伏せるところからはじまる。
父親である大旦那の気がかりもひとかたならず、評判の名医にもたのむのだが、若旦那の身体の不調の原因はわからずじまい。
名医の見立てでは、どうやら心の病、若旦那の心中には深く秘めたる思いがあるようで、これを紐解かないことには回復は見込めないという。
心の問題ならばと、おまえさんのその胸中、どうにか受けとめてやろうと大旦那も気を揉むが、じつはこの若旦那、生来の内気かつハニカミ屋な性分で、親に本心を打ち明けることを極度に恥ずかしがり、ただただうつむき、床に伏せって、やつれていくばかりである。
とはいえ、このまま指をくわえて看ているばかりではいられない。
やっとのことで若旦那から言質をとりつけたのが、幼馴染である出入りの職人・熊五郎にならば、その心中を明かすというものだった。
さっそく熊五郎を呼びつける大旦那。
ところが、このクマさん、ガサツ、無神経が顔に張り付いたような男で、繊細な若旦那とは正反対の性分である。
床に伏せったわが息子を気遣って大声を出すなと言っているのに、あいさつ口上もやたらと声がでかい。
あらためて親から見ても、なぜにこの二人の仲が良いのだろうかといぶかりつつも、とにもかくにも、ここはどうして、このクマ公にまかせるしかない。
ということで、すっかり萎れて床についたままのダウナー若旦那と、ムダに声がデカいハイテンションなクマとの会話がはじまった。
「どうしました、若旦那。病名がわからないっていうじゃありませんか」
「ふう。医者にはわからなくっても、あたしにはわかってるんだよ」
「なんだい、そうなのかい? 医者にはわからないのに、若旦那にはわかるって? どういうこってすか?」
「ほんとうは誰にも言わずに死んじまおうかと思ったんだけど、せめて、おまえさんだけには言っておこうと思って。……けれど、あたしがこんなこと言ったからといって、おまえさん、笑っちゃいけないよ」
「冗談言っちゃいけねぇや。人の病いを聞いといて、笑うなんて奴があるもんですか。さあ、なんなんです? 言ってごらんなさい」
「……ほんとうに笑わないかい? そんなこと言っておいて、笑うんだろう。あたしは笑われでもしたら、それこそ恥ずかしくて死んじまうよ」
「だから、笑いませんって。ええ、笑いませんとも」
「しかし、ねぇ、そうはいっても、あたしがこんなことを言ったら、えへへ、やっぱり笑うんだろうねぇ、えへへ……」
「言ってる本人が笑ってりゃぁ、世話ねぇや。若旦那、あっしは笑いはしませんから、言ってごらんなさいよ、ほら」
「そうかい? ほんとうに笑わないかい? じつは……、じつはねぇ……、あたしの病ひは……、恋わずらい……」
「だっははは!」
「ほら! やっぱり笑ったじゃないか!」
「すんません、すんませんって。もう笑いませんってば! しかし、まあ、また、恋わずらいとは……、いまどきたいそうな病をしょいこんじまって……。いったいぜんたい、どういうことなんです? なにがあったんですか?」
若旦那の話では、ひと月ほど前、花見に出かけた際に、たまたま茶屋で出会ったどこかのお嬢さんにひと目惚れしたのだという。
このお嬢さん、水もしたたる美貌だったそうで、見とれる若旦那にニコリとはにかみ、やがて立ち上がって帰ろうとするが、膝からハラリと袱紗が落ちたことに気がつかなかった。
これを拾い上げて手渡す若旦那。頬を染めながら礼をいうお嬢さん。
するとこのお嬢さんは茶屋の店主に料紙を求め、なにごとかしたため始めた。
別れ際、「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の」としるした短冊を若旦那に手渡して行ったが、これは百人一首にある崇徳院の歌で、下の句が「割れても末に逢はぬとぞ思ふ」となる。つまりは、「今はここで別れても、後にかならず逢いましょう」という心だとして、若旦那、おもいっきり舞い上がってしまったのだ。
そう。とどのつまりは互いに一目惚れ、両想いだったわけである。
「その歌をもらって帰ってきたんだがね、それからというもの、なにを見てもお嬢さんの顔にみえるんだ……、掛け軸のだるまさんがお嬢さんに見える、花瓶の花がお嬢さんに見える、鉄瓶がお嬢さんに見える、おまえの顔までがお嬢さんに見える……」
「だあっ! 近いってぇの、近寄りすぎだよ、若旦那! 気味がわるいったりゃありゃしねぇ。それにしても、ひどくおもいつめたもんですな。よござんす。あっしも男だ。ここは、ひとつ、若旦那のために一肌脱いで、なんとか一緒にしてさしあげましょう。で、お相手は、どこの方なんです?」
「それが、その……、わからないんだ……」
困ったことに若旦那、あまりの出来事に息を呑んで惚けるばかりで、肝心要をしくじった。所番地でも聞いておけばよいものを、相手がどこのお嬢さんなのかわからないという。
さあ、どうする。
話を持ち帰ったクマが、大旦那に顛末を話す。
「よくぞ聞き出してくれたね、クマさん。ありがとう、せがれの命の恩人だ。あれがそれほど思い詰めたお嬢さんなら、なんとしてでも、もらってやらねばなるまい。で、クマさん、たのまれついでに、先方へもかけあってくれるんだろうね」
「は? いや、旦那。そりゃあ、乗りかかった舟ですし、若旦那のためだ、やぶさかじゃぁありませんが、ですが、そのお嬢さんなんですが、どこの方だかわからねぇわけで……」
「わからないといっても、日本人だろ」
「そりゃあ、そうでしょうけれども……」
「それなら、まずは江戸じゅうをさがしてごらんなさいよ。それで見つからなければ、横浜。横浜でわからなければ、静岡、浜松、名古屋、大津に、京都、大阪。しらみつぶしに捜したとあらば、いずれは見つかるでしょうよ。見つけてくれたならば、先月、お前さんに貸した金、あれは棒引きにしようじゃないか、ええ。それから、いまお前さんが住んでいる三軒長屋、あれもつけてやろう」
「へえ、そりゃあ、ありがてぇお話ではありますが、ですが、なにしろ雲をつかむようなことですし……」
「おい、定吉や、そこにわらじが十足ばかりあるだろ。かまわないから、それをクマさんの腰へぶらさげちまいな。たのみましたよ、クマさん」
大旦那に押し切られて、泣く泣く長屋に戻るクマ。
長屋では女房にも「この三軒長屋をくださるのかい。あーら、運がむいてきたわね。おまえさん、しっかりと捜してきておくれよ。はやくいっといで!」と不承不承も丸め込まれて、家からもたたき出される。
と、その日から、若旦那のため、クマ公の遮二無二のお嬢さん捜索行が始まったわけだが、なにせ、手がかりがない。
足を棒にして、まるまる二日間を棒に振るも、カミさんから「おまえさん、どんな捜し方をしてるんだい?」と尋ねられて、言葉に窮するクマ。
「いや、それは、その……、このへんに水の垂れる方はいませんかって……」
「なにやってるんだい! ドザエモン捜してるんじゃないんだよ。それじゃ、わかるわけないじゃないか。おまえさん、旦那に歌を書いてもらったんだろ。それがなによりの手がかりじゃないか。それを往来で大声で唱えながら歩いてごらんよ。そうすりゃ、それを聞いた人が、声をかけてくれるはずさ。それでもだめなら、お湯屋とか、床屋とか、人の集まるところへ行って、どなってごらんよ。だれかが、その歌についてはこんな話がありますとか、こんなうわさを聞きましたとか、おしえてくれるはずさ」
手弁当片手に、今日も往来をあてどもなく歩きまわる熊五郎。
「瀬をはやみぃ〜、岩にせかるる滝川のぉ〜」
「ちょいと、豆腐屋さん」
「だぁっ、ちがうちがう。人を豆腐屋とまちがえやがって。あぁ〜あ、それにしても、とんだことをひきうけちまったなぁ。この調子じゃぁ、若旦那よりもおれのほうが先に逝っちまうぜ、とほほ……。しょうがねぇ、かかぁの言ってたとおり、河岸でも変えるか」
その後、熊五郎、湯屋や床屋などをあてに渡り歩いて捜し求めるも、いっこうに手ごたえがない。
「いらっしゃい」
「こんちわ。混んでますか?」
「いえ、いまちょうどすいたところで」
「さよなら」
「ちょ、ちょっと、お客さん! すいたんですよ! すぐにやれるんですよ!」
「ちっ、すいてちゃいけねぇんだよ。こちとら都合があるんでぇい。……よし、この床屋はどうかな? こんちわ。混んでますか?」
「ええ、ごらんのとおり。五人ほどお待ちなんで、ちとつかえてますから、後ほどいらっしゃるとありがたいんですが……」
「いえ、そのつかえているところを捜していたんで」
「はい?」
「あー、あー、えへん、ちょいと失礼して、やらせてもらいます。瀬をはやみぃ〜〜〜」
「うわ! びっくりしたな、もう! なんだい急に、大声なんか出して」
「もし、あなた、それは崇徳院さまの御歌では?」
「(!) よ、よくご存知で!」
「ウチの娘が近頃それをよくやってますよ」
「(!) ひょっとして、ひょっとすると、おいくつなんで?」
「八つです」
(ガクッ)
湯屋を十八軒、床屋を三十六軒、さんざん髭も剃りたおして、わずかっぱかしも生えていない。
夕刻の頃合いになり、もうフラフラ、それでも今朝一度顔を出した床屋にフラフラと迷い込んでヘタリ込んでいると、フラっと鳶職風の男が店に飛び込んできた。
「おう! 親方、ちょいと急ぐんだけど、やってもらえねぇかい? あ、待ってる人がいるのかい。まいったなぁ」
「あっしのことですか、ええ、あっしならいいんですよ。もう、どこも剃るところがないもんですから……」
「そうなのかい? すいませんねぇ、じゃ、親方、ひとつたのんまさぁ」
「はいよ。しかし、ばかに急ぐんだねぇ」
「ああ、おタナの用事でね」
「おタナといえば、そういえば、どうなったんだい? お嬢さんの具合のほうは?」
「それがなぁ、かわいそうに、どうやら、もうあぶねぇんだと……」
「そうかい、あぶないのかい。 気の毒に……、あの小町娘がなぁ……」
「ああ、旦那もおかみさんもまいってるみたいで、見ちゃいられねぇよ」
「けれど、お嬢さんは、いったいなんの病なんだい?」
「それが、いまどき珍しいことに、恋わずらいなんだとよ……」
「瀬をはやみィッ!!!」
突然、クマにむしゃぶりつかれて、びっくり仰天のトビ。
「お、おい! いきなり、なにしやがる!」
「三軒長屋……三軒長屋……」
「おいおい、気味の悪い念仏なんか唱えて、なんなんだい、親方ヨォ、このやっこさんは!」
「てめぇに逢おうがために、艱難辛苦如何ばかり……、瀬をはやみィ、岩にせかるる滝川のォ……」
「お、おい! てめぇ、なんでその歌を知ってやがる! なに! てめぇのところのお店の若旦那が? こりゃぁ、いいところで出会ったもんだ! もう少しで、こっちも江戸の外を捜すはめになるところだった。おれもおめぇを離さねぇぞ! さぁ、おれんとこのおタナへ来いってんだ!」
「なにをいってやがんだいっ! おめぇこそ、ウチのおタナまで来い!」
「なにおぅ! てめぇこそ!」
「なにおぅ! おめぇこそ!」
「おいおい、よしな、よしな、よしなさいってば! はなしをすればわかるてぇの! お、おい! あぶねぇ、あぶねぇ!」
互いに引っ張り合うクマと鳶のなにがし。
おたがいに自分の店に連れ帰ろうと引き摺りあったあげく、はずみで、大きな花瓶が倒れて、前にあった鏡をぱりんと割ってしまう。
「そら、やっちまった! いわんこっちゃない。鏡をこわして、商売あがったりだよ。どうしてくれるんだい?」
「いや、親方、心配しなくてもいい」
「なぜだい?」
「割れても末に買わんとぞ思う」でサゲ。
◾️ 落語のことば補説
▼ 袱紗(ふくさ)
方形の絹の布。もともとは「掛袱紗(かけふくさ)」として、慶事・祝事の贈答品を持参する際の道中での日除けや塵除けに用いられたが、江戸時代になるとこの覆い布が発展して、裏を付けた二枚合わせとなり、さまざまな用途で使われるようになったそうだ。
ちなみに茶道でも用いられ、「帛紗」と書き、懐中に携帯して茶碗の下に敷いたり、盆や受け皿の代用として用いられる(小袱紗)。
江戸期の袱紗の有名な刺繍に「紺繻子地鯛模様」(こんしゅすじたいもよう)というものがあり、これは二尾の鯛を結わえる綱の端を扇のように開いて熨斗のように見せるデザインをしており、大きな目の「目出鯛」が向かい合わせで「夫婦仲良くおめでたい」という意味が込められていて、袱紗を出会いのきっかけとするこのネタの伏線を暗示させる。
▼ 崇徳院/「瀬をはやみ岩にせかるる滝川の割れても末に逢はぬとぞ思ふ」
百人一首にも収められた有名な歌で、出典は『詩歌和歌集』。「瀬をはやみ」は「川の浅く流れの速いところ」で、「岩にせかるる滝川の」は「岩に堰き止められた滝のように流れの速い川」の意。「割れても末に逢はぬとぞ思ふ」は岩にせきとめられて「川の流れが二つに分かれようとも、ゆくゆくは一つになる」ように、これを別れた男女にかけて、「今は離れ離れになったとしても、ふたたび出逢いましょう」という想いを歌った句である。
崇徳院、崇徳天皇は第七十五代天皇で、保元の乱で有名。後白河天皇と争うも敗れ、讃岐松山へと配流となるが、生涯これを恨み、舌を噛んで流れ出た鮮血で「願わくば大魔王となって天下を悩乱せん」という、すさまじい怨念も記した人物だったそうだ。「瀬をはやみ」は乱以前に詠んだ恋歌だが、そこには一途、激烈な情念が込められていて、落語のほうでは、そこまで互いに好き合って床にまで伏せってしまうという、恋煩いの伏線ともなっている。
▼ 床屋
式亭三馬の滑稽本『浮世床』にもその様子が活き活きと描かれているとおり、床屋は江戸期において銭湯とともに町内のクラブ、サロンとして親しまれていたようである。
落語のほうでの「浮世床」、ほかに「無精床」「崇徳院」などの舞台ともなっており、当時、原則として一町内に一軒と限って許可された床屋(内床という)は資格制で、建屋の階上が町内の会所となっている床屋も多く、床屋の親方(主人)が町奉行所同心の手先もつとめたそうだ。髪結いだけを生業としていなかったわけである。
◾️ 鑑賞どころ私見
「恋わずらい」という、古風この上ない題材をあつかった噺だが、それだけにというか、江戸期のなんとものんびりとした時代の雰囲気が伝わってきて、いかにも落語らしい、ほのぼのとした作品である。
恋する若旦那とお嬢さんのあいだでドタバタする周囲の人たちがいっそのことほほえましく、現代ではありえないような他人様のために徒労を買って出る、おおらかな"世間"の在りように憧憬の念すら覚える、和気藹々とした滑稽噺である。
上記、あらすじのほうでは割愛させてもらったが、この噺の演出で、若旦那の余命が幾許もないという設定を強調する噺家もいる。
若旦那の命が五日も持たないということから、熊五郎は大旦那から三日で捜してこいと命じられ、なおいっそうせわしない展開でもって聴衆をいっきに惹きつける演出もあれば、他にも、熊五郎が床屋と湯屋を何軒もまわるハメになることから、ほうぼうでヒゲを剃られて、ツルツル、テカテカになってしまうという面白い演出もあったりする。
各噺家の視点と力量でいかようにも面白くなってしまう噺なので、ぜひにそれぞれご賞味していただきたい演題でもある。
この噺は上方落語中興の祖である初代・桂文治の作で、上方落語の代表作というふれこみになるが、江戸前にも「皿屋」「花見扇」などの題で、ほとんど同じストーリーの噺があったそうだ。
また落語の別の演題で「三年目」という人情噺があるのだが、この噺がその発端部分だという説もある(五代目円生などの速記本に当たると、「三年目」の冒頭部が恋わずらいから始まるとされている)。
ここでいちおう、サゲの解説を少々しておくと、いわゆる崇徳院の歌の下の句の洒落であり、「鏡が割れても、月末に(末に)、買わん(弁償しよう)とぞ思う」ということなのだが、江戸時代も支払いが一般的に月末(三十日払い(みそかばらい))であったことがうかがえて、なかなかどうして興味深いものがある。
またサゲにもいくつかのバリエーションがあるそうで、取っ組み合いになった際、熊五郎が相手の「手を放しやがれ」という言葉に対し「いいや放さねぇ(われても末に)、合わすんだ(あわんとぞ思ふ)」と、やはり下の句を押さえた返しで落とすものや、また「皿屋」題の場合、舞台が床屋から皿屋になって、鏡ではなく品物の皿を割るというかたちになって〆たりするそうである。
ちなみに、この噺のように、落語のなかで百人一首を題材にした噺は、「千早振る」など、わりと多く見かけることも付記しておく。
余談になるが、そういうことなので、落語きっかけで百人一首の世界に入る人もけっこういるとかいないとか。
いずれにしても古典全般の勉強の入り口として、落語の世界はそのきっかけとなる事柄を多く与えてくれるものと個人的には感じている。
話を戻すと、この演目をオハコ(十八番)にしていたのは、東京では三代目桂三木助だったそうだが、個人的に聴いていただきたいイチオシの噺家は、三代目古今亭志ん朝である。
この噺の決定版ともいえる、出色の出来栄えだと思うので、是非に YouTube などでご鑑賞されたい。
それにしても昨今、若者の"恋愛離れ"という話題が巷にあがっているのを見るにつけ、人のことを好きになってしまうことに離れるもなにもあったものだろうか、と思ってしまうのだが、こういった感想も古びてみられるのならば、なんとも寂しい風潮になったものだと、この噺を聴いていてふと感じてしまう今日この頃である(「崇徳院」に触れた以下、【随想】記事はこちら)。
◾️ YouTube 視聴
▼ 映像あり
・笑福亭松喬[六代目]:https://www.youtube.com/watch?v=ArVb59hKAww
・金原亭馬生[十代目]:https://www.youtube.com/watch?v=HcaiyUNHTzs
・三遊亭小圓遊[四代目]:https://www.youtube.com/watch?v=XKWRweTU478&t=88s
▼ 音声のみ
・古今亭志ん朝[三代目]:https://www.youtube.com/watch?v=MO-f3S1r1KY
・桂三木助[三代目]:https://www.youtube.com/watch?v=o8L_rUU2n4g
◾️ 参照文献
・矢野誠一『落語手帖』(講談社+α文庫、1994年)
・京須偕充『落語名作200席(上・下)』(角川文庫、2014年)
・榎本滋民 著、京須偕充 編『落語ことば・事柄辞典』(角川文庫、2017年)
・興津要 編『古典落語』(講談社学術文庫、2002年)
・立川志の輔 選/監修、PHP研究所 編『滑稽・人情・艶笑・怪談… 古典落語100席』(PHP文庫、1997年)