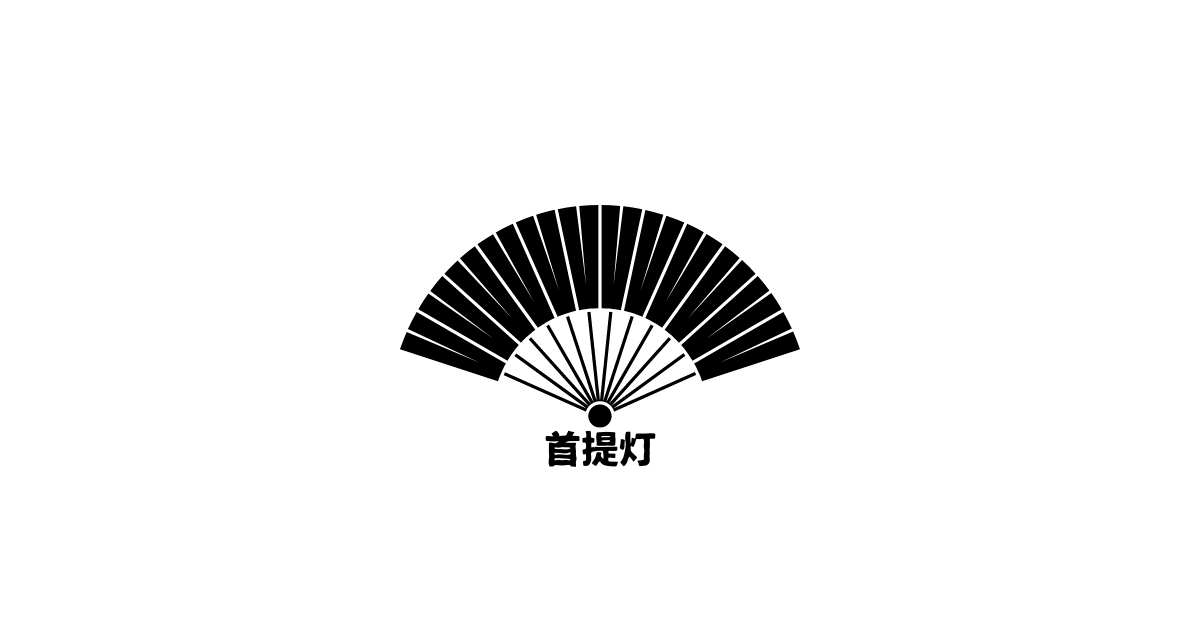
落語のなかの奇想天外、シュールな噺は江戸前のほうに多いといわれますが、この「首提灯(くびぢょうちん)」という噺もそれにあたります。
意味深なタイトルで、一見すると怪談を想起するかもしれませんが、そこは一味違います。奇々怪界であることにはかわりませんが。
しかもこの噺は仕方噺(仕草噺)の代表格。寄席で噺家が演じる雰囲気をまるごと味わってほしい、いわゆる"落語らしい"ストーリーとなっています。
◾️あらすじ
噺は増上寺近くの芝山内で辻斬りが出没するとの噂から始まる。
芝山内は品川の廓への道すがらにある寂しい場所で、そこを噂など意にも介さぬふうの酔っ払いがひとり、酔興も良い頃合いで歩いていた。
とはいいつつも内心、じつは怯えている。
が、こちとら江戸っ子である。
冗談じゃねぇ、出れるもんなら出てきやがれ、辻斬りめッ!
強がりもたいがいだが、酒の勢いもあり、侍ふぜいに日頃の鬱憤、思わぬところもなきにしもあらずで、あたりにわめき散らしながら怖さを紛らわせている。
すると「おい、町人」。
出た!
闇夜にふらりと大小をたばさんだ巨躯があらわれる。
すわ襲われるかとヒヤッとなるも、どうやら江戸へ出府したての田舎侍のようで、麻布への道順を尋ねてきた。
「なんでぃ、おどかすねィ」
ホッとため息をつきつつも、おどかされたという癪もあってか、いちど火のついた先ほどからの悪態がなかなかどうして止まらない。
酔狂はしくじりの素である。
目上に対するも、その横柄な態度は田舎者だからなのか、丸太ん棒めと、ひと言多く突っかかる。
ひと様にものを尋ねるのならば、いくらサムライであっても、もっと殊勝にしやがれ、とこれみよがしにうそぶく始末。
さんざん毒づいた挙句、とどのつまりは墓穴を掘ることに。
これでもかという無礼口上を酔いの上だと我慢に我慢を重ねていた侍のほうだったが、こと家紋の服に啖呵を切られては、おだやかでいられない。
堪忍袋の緒も切れようものである。
白刃一閃。
居合い抜きで、喰ってかかった酔っ払いの首をすっぱ抜く。
が。
あまりに見事な腕前だったので、この酔っ払い、素っ頓狂なことに、首を刎ねられたことに気づかなかった。
足早に立ち去る侍を背に、ひと騒動おわってもいまだ首を斬られたことに気づく様子もない自業自得のこの酔漢。
鼻歌などを歌って調子よく残りの夜道を流しているのだが、なぜだか息が洩れる、視界がズレる、だんだんと首が定まらなくなる、千鳥足ならぬ千鳥首とあいなる。
今晩は酔いのまわりも早いのかな、などとぼやきつつ、呑気なことこの上ない。
が、何遍か首の曲がりを直していると、首筋に血糊がべっとりと。
おいおい、まさか、こりゃぁ、やられたのか、いや、やられていたのか!
痛くも痒くもなかったってぇことは、あの侍、手練の早業のことよ、達人なのか、と妙な感心もしたりする。
ともすれ、首を落としちゃ、てぇへんだ、膠(にかわ)でもつけとけば大丈夫かしら、じゃなかった、どうするよ、おい!
と、気づいたときには後の祭りである。
が、くしくも間が悪いときとはあったもので、火事場騒ぎで人だかりができているところにばったりと出くわす。
行く手には、手に手に提灯かざして火事場へと駆け寄せる野次馬だかり。
火事と喧嘩は江戸の華である。
火事とあっちゃぁ、この酔っ払いの血も騒がずにはいられない。
首のことそっちのけで、一目散に火事場の渦中へと駆け出して、人だかりを向こうに両手で自分の首を前へかざして、提灯よろしく「はい、ごめんよ!ごめんよ!」でサゲ。
◾️落語のことば補説
▼ 増上寺・芝山内
芝山内は大半が三縁山広度院増上寺の境内で、江戸期は景勝地として知られた。現在の東京都港区芝公園。
▼ 辻斬り
「つじぎり」とは文字どおり、武士などが街中などで通行人を刀で斬りつけることをいう。つまりは「通り魔」である。
江戸前期に頻発したそうで、徳川幕府はもちろん犯人に厳罰を処した。凶刃に及んだ者は死罪である。
辻斬りの犯行理由はさまざまで、刀の切れ味を実証するための「試し斬り」や、たんなる憂さ晴らし、金品目的、自分の武芸の腕を試すなどがあったそうだが、被害にあった善良な江戸町民たちからすれば不条理きわまりない帯刀社会の現実がそこにあったわけだ。
▼ 田舎侍
大名の家臣には、地方の国元に仕える「国侍(くにざむらい)」と、江戸の藩邸に常詰めする「定府侍(じょうふざむらい)」とがあったが、前者は参勤交代に従って出府し、江戸藩邸に一定期間住み込みで出仕するため「勤番侍(きんばんさむらい)」とも呼ばれた。
この勤番侍、短期の江戸滞在で、給金も安かったということもあり、散策や遊興も満足にできず、当然のことながら江戸不案内で、着物や羽織の裏地に丈夫一遍の浅葱色(あさぎいろ・緑がかった薄い藍色)の木綿を用いていたところから、江戸の町民たちからは野暮な「浅葱裏(あさぎうら)」と軽蔑されていた。
首提灯で、たんなる町人風情の酔っ払いが喰ってかかったのには、こういう背景があったからである。
実際、江戸期の各藩の財政は常時逼迫しており、江戸に住む庶民から「田舎侍」と揶揄されるとおり、勤番時にはかなり惨めな生活を送っていたようだ。
小遣いは一日百文以内に切り詰め、駕籠にはけっして乗らず、蕎麦屋で蕎麦湯をがぶ飲みして腹の足しにし、酒も安くて強い焼酎ばかりをあおるという緊縮ぶり。飯屋にさえ入れず、露店の焼き芋でしのぐという「芋侍(いもざむらい)」の惨めさで、素町人以下の"寒い"ふところ具合を、「サンピン野郎」「駄サンピン」(三両一分の扶持(薄給)を"サンピン"といった)とさげすまされていたそうである。
▼ 火事と喧嘩は江戸の華
江戸時代、史実によれば「火災都市」といわれるほどに火事が頻発し、さまざまな理由によって市街地を広範囲にわたって繰り返し焼き払った歴史的大火が世界でも類例を見ないほど多かったそうだ(Wikipediaより)。
「火事と喧嘩は江戸の華」という言葉の由来には諸説あるようだが、字ヅラのとおり、火事と喧嘩を見世物・娯楽としてとらえていた江戸庶民のしたたかさが垣間見れるような含意ももちろんあるが(実際、火事の様相を紅葉に見立てた風流もあったそうだ)、"喧嘩"のほうは、たとえば酔っ払い同士が肩をぶつけて始めるような程度の低い諍いを指すものだけではなかったようである。
この場合の喧嘩とは江戸庶民の誇りをかけた消火活動、火消し同士の火事場あらそいを指すものとしてとらえたほうが意味に奥行きが出そうだ。
まず、この時代の消火活動は放水による鎮火がメインではなかったそうだ。延焼を阻止するための周辺建屋の撤去、火の風下に立つ家屋を倒壊してまわるのほうに主眼がおかれたようである。
要するに起きてしまった大火のまわりから、いっさいの可燃物を取り払うことが主目的とされたわけで、江戸の火消しが大工さながらの「鳶(とび)の者」とされたのは、これがためだ。命懸けで家を叩き壊してまわったわけである。
ここいらへんに江戸っ子の手荒な「ガラッパチさ」の由縁がありそうだが、つまりはワッと燃え盛る紅蓮の大火を非日常を演出する舞台装置としてとらえ返すのならば、そこに町人火消し同士の看板を背負った対抗意識、ひいては舞台廻し(喧嘩)としての華があり、火事場という舞台にこそ庶民の生活を守った火消しの意地と心意気があったと見るべきだろう。
他方では、火事は江戸の華の語源を大老酒井忠清の言にありとする説もある。
あまりの火事の多さにかの老中が「かように火事を起こすは江戸の恥」と洩らしたのを講釈師ないし狂歌師がすり替えたのが、「江戸の華」のいわれとする説である。
"恥の上塗り"を「華」とかぶせてケロりと煙に巻くあたり、いずれにしても江戸庶民の逞しき精神性を感じさせる言葉であることは確かなようだ。
◾️鑑賞どころ私見
江戸落語のほうに多い奇想天外ネタ、シュールな小噺のひとつである。
酔っ払いの酩酊ここに極まれりとでもいおうか、あまりにもあざやかな斬り口に気づかずに首の座りのわるさを訝しんで首をウンウンと捻るあたり、やはりなんともおかしい。
この演題も仕方噺(しかたばなし)のひとつで、噺家の仕草、身振り・手振り付きで鑑賞することをおすすめしたいが、実際に首がズレていく様は噺家の腕の見せどころときている。
寄席に出かける際に演目に掛かっていると個人的にちょっと楽しみだなと思ってしまうネタのひとつである。
この噺のサゲについては、じつは噺家によって幾つかのパターンがある。
上記あらすじのサゲは三遊亭圓生の演出によるもので、火事を見物する人びとの雑踏にまぎれて首を落っことしそうになるのをひょいっとかつぎあげる、おまけに人だかりの向こう側を高いところから遠目で見ようとついに首そのものを持ち上げるところに、なんともいえない笑いの余韻がある。
一方で、林家正藏(彦六)流のサゲというのもあって、こちらの場合は首を斬られたまま火事見舞に駆けつけるという演出で、目的のタナの店先で「へい、八五郎でございます」と提灯がわりに自分の首を威勢よく差し出すサゲとなっている。
こちらも、この酔っ払いのすっとぼけたおかしみが感じられて、捨てがたい魅力がある。
いずれにしても、道往く人びとがみな提灯を掲げているなかで、この酔っ払いだけがただひとり己が首を提灯がわりにかかげて、あせって駆け出している馬鹿馬鹿しさに、想像するだに笑ってしまう。
念のために言っておくが、これを真顔でとらえてホラーだと思うのは野暮の骨頂である。
あるいは、首を斬られていることに気がついているのに、なんでわざわざ火事見舞いにまで行くのかなどと、さかしまな理屈をふりかざしてはならない。なにも考えずに、アッハハと笑うのが正しい落語鑑賞の姿勢である。
それにしても、むかしも今も酔っ払いの始末のおえなさについては、ここであげつらうまでもない(このブログでも別のところで少々触れさせてもらったが)。
この噺、酒呑みのしくじりを諫める教訓としても聴けはするが、まあ、それでも、そういうスキだらけの醜態にどことなく"可愛げ"を看取ろうとするまなざしが落語の噺のなかには共通してあって、「しょうがないねぇ」とあきれつつも、あまねく酔っ払いにどこか優しいところに、人の世の救いのようなものをそこはなとなく感じてしまう。
落語のそんな世界観こそが、人を惹きつけてやまない魅力のひとつであることは、現在をもっても確かなことなのである。
◾️YouTube 視聴
▼ 映像あり
・林家正蔵(彦六)[八代目]:https://www.youtube.com/watch?v=oFXD8GJTALM
・笑福亭松喬[六代目]:https://www.youtube.com/watch?v=-CB2q88NI_s
*上方落語では同じ演題でも江戸前とストーリーがまるで異なることがある。「首提灯」もそれにあたるのだが、首を提灯に見立てるサゲは同じだ。聴き比べをして、双方それぞれの魅力を味わってみてほしい。
▼ 音声のみ
・三遊亭圓生[六代目]:https://www.youtube.com/watch?v=o0dna0-yCuI
・古今亭志ん朝[三代目]:https://www.youtube.com/watch?v=hBsF9AL_TqM
◾️参照文献
・矢野誠一『落語手帖』(講談社+α文庫、1994年)
・京須偕充『落語名作200席(上・下)』(角川文庫、2014年)
・榎本滋民 著、京須偕充 編『落語ことば・事柄辞典』(角川文庫、2017年)
・立川志の輔 選/監修、PHP研究所 編『滑稽・人情・艶笑・怪談… 古典落語100席』(PHP文庫、1997年)